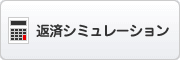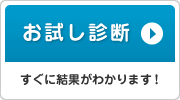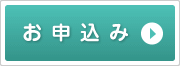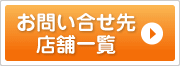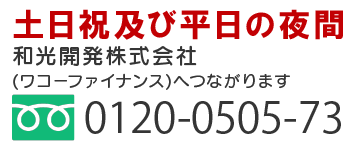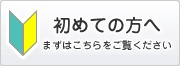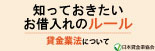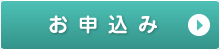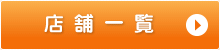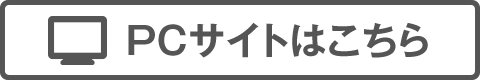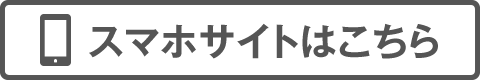金融トラブル、費用をかけずに早期解決!金融ADR制度をご利用ください
私たちの生活に身近な、預貯金や保険、証券などの金融商品・サービス。これらの取引をめぐって金融機関との間で、トラブルが生じたことはありませんか。そのようなときに利用できるのが金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)です。裁判以外の手続きで、費用をかけずに、迅速にトラブルの解決を図ります。
利用者と金融機関とのトラブルを、裁判以外の方法で解決を図る「金融ADR制度」
銀行の預貯金や生命保険、損害保険、株式や債券、投資信託など、金融商品・サービスの多様化・複雑化が進む中で、利用者と金融機関との間で、金融商品・サービスに係るトラブルが多くなっています。
こうした金融トラブルを解決するため、銀行・保険・証券などの業界団体等において、従来から自主的な苦情処理・紛争解決の取り組みが進められてきましたが、中立性・公正性、実効性などの観点から、必ずしも万全ではなく、利用者からの信頼が十分得られていない面がありました。また、トラブルを解決するために、「裁判」で争うという方法もありますが、裁判には費用も時間もかかるという問題もあります。
そこで、平成21年の「金融商品取引法等の一部を改正する法律」により、利用者保護・利用者利便の向上のため、裁判よりも費用や時間がかからず、金融分野に見識のある弁護士等の中立・公正な専門家(紛争解決委員)により、金融トラブルの解決を図る「金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)」が、国の制度として創設され、平成22年10月1日から本格的にスタートしました。
全国の消費生活センター等に寄せられた「金融・保険サービス」に関する相談件数

グラフは「消費生活年報2010」(国民生活センター)のデータをもとに作成。なお、システム上の改定を行ったため、2008年度以前と2009年度以降での単純な比較はできない。
注:金融・保険サービスに関する相談件数は、2003年10月のヤミ金融対策法の施行により、いったん減少したものの、全体としてみると増加傾向にあります。
金融ADR制度の3つのメリット
金融ADR制度は、金融機関との取引に関して、利用者と金融機関との間でトラブルが発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)にかかわってもらいながら、裁判以外の方法で解決を図る制度のことです。
金融ADR制度には、次のような3つの大きなメリットがあります。
(1)中立・公正
金融ADR機関に所属する金融分野に見識のある弁護士等の中立・公正な専門家(紛争解決委員)が和解案を提示し、解決に努めます
(2)迅速
金融ADRによる紛争解決までの標準的な処理期間は2~6か月程度で、裁判よりも短期間で解決することができます
(3)低コスト
各金融ADR機関によって利用料が定められていますが、一部を除き、無料です。詳しくは各金融ADR機関にお問い合わせください。
金融ADR機関は業態ごとに設立されています
「保険金を受け取ったが、金額が契約金より少なく、納得がいかない!」「金融機関の勧めで金融商品を購入したが、大損した。契約時には元本割れの説明はなかった!」など、金融トラブルを抱えながら、「弁護士に相談したいけれど、費用がかかる」と悩んでいる方は、金融ADR制度を利用してみてはいかがでしょうか。金融ADR機関が、当事者双方の話を聞きながら、時間や費用をかけずに、中立・公正な立場で紛争の解決を図ります。
金融ADR機関は、業態ごとに設立されています。金融ADR制度を利用するには、取引先の金融機関またはその金融機関が契約している金融ADR機関にお問い合わせください。
業態によっては、金融ADR機関が設立されていない場合もありますが、そのような場合においては、金融機関自らが苦情処理・紛争解決の対応を図るための体制整備を行わなければなりません。詳しくは、取引先の金融機関または業界団体にお問い合わせください。

- ・金融ADR機関一覧はこちらをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/adr/shiteifunson/index.html - ・金融ADR機関が設立されていない業態はこちらをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/adr/shiteifunson/kikannashi.html
金融機関は、金融ADR機関から提示された和解案を原則受け入れなければなりません
金融ADR機関では、利用者からの金融商品・サービスに関する相談や苦情を、電話や窓口で受け付けています。金融トラブルが当事者同士における話し合いで解決せず、利用者が金融ADR制度での紛争解決を希望する場合には、金融ADR機関に紛争解決の申し立てができます。申し立てをする際の書類の書き方なども金融ADR機関がサポートします。
利用者が金融ADR機関に紛争解決の申し立てをした場合、金融機関は、利用者からの紛争解決の申し立てに応じなければならないことになっています。
利用者からの申し立てを受けて、金融ADR機関は、中立・公正な立場で、双方から話を聞き、和解案を提示します。金融機関は、金融ADR機関によって提示された和解案を、原則受け入れなければならないことになっています。
ただし、金融ADR機関はあくまでも中立・公正な立場で和解案を作成しますので、利用者にとって自分の思いどおりの和解案になるとは限りませんので、ご留意ください。
金融トラブルの原因は、利用者側にあるケースも少なくありません。トラブルを未然に防ぐためにも、金融商品・サービスを契約するときには、金融機関の説明をしっかりと理解し、納得してから行うようにしましょう。
利用手続きの一般的な流れ(概要)

<取材協力:金融庁 文責:政府広報オンライン>