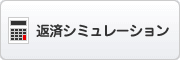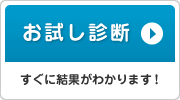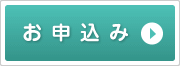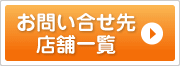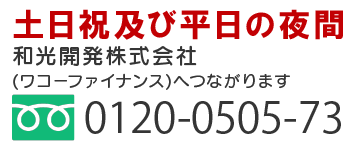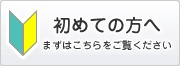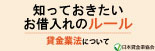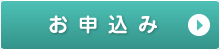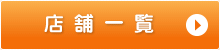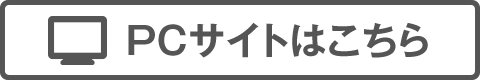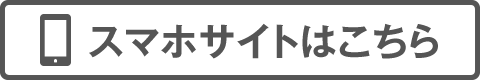老後に固定資産税が払えないとどうなる?滞納リスクと対処法・調達方法を解説

「年金中心の生活になってから、固定資産税の負担が以前より重く感じられるようになった…」と悩みを抱える方は少なくありません。住宅ローンを完済しても、不動産を所有している限り税金の支払いは続くため、収入が減った家計では負担が大きくなりがちです。
また、固定資産税を払えないまま放置すると延滞金が加算され、最終的に財産が差し押さえられる可能性もあります。しかし、早めに対処すれば十分に回避できる方法があることをご存知でしょうか。
この記事では、老後に固定資産税の支払いが難しくなる理由や滞納のリスク、そして現実的な対処法までを分かりやすくまとめています。不安を減らし、安心して次の一歩を踏み出せるように解説します。
そもそも固定資産税とは?老後もゼロになることはない?
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を持っている人に課される地方税です。毎年1月1日時点で所有者として登録されている人に納税義務が生じます。
対象となるのは土地、家屋、そして事業用の償却資産の3つで、一般家庭では自宅の土地と建物が主な対象です。
| 分類 | 対象 |
| 土地 | 田、畑、住宅地、塩田、鉱泉地(温泉など)、池沼、山林、牧場、原野などの土地 |
| 家屋 | 住宅、店舗、工場(発電所や変電所を含む)、倉庫などの建物 |
| 償却資産 | 会社・事業者が所有する構築物(広告塔やフェンスなど)、飛行機、船、車両や運搬具(鉄道やトロッコなど)、備品(パソコンや工具など) |
固定資産税は、固定資産税評価額に標準税率1.4%を掛けて算出されます。評価額は3年ごとに見直され、市場価格(実勢価格)とは異なる方式で計算されるため、一般には売買価格よりも低く設定される傾向があります。
建物の評価額には、構造や築年数に応じて経年減点補正が適用されます。
【建物の評価額の特徴】
- 年数が経つほど評価額は下がる
- とくに木造住宅は下落幅が大きく、最終的にはかなり低い額になることもある
- ただし、制度上、家屋の評価額がゼロになることはない
なお、課税標準額が家屋の免税点(20万円)を下回る場合は固定資産税が課税されません。
また、年金生活に入ったからといって自動的に固定資産税が免除される制度はありません。
老朽化の末、建物として評価できないほど崩れてしまわない限り、課税は続きます。
出典:総務省「固定資産税」
老後に固定資産税が払えなくなるケース
老後に固定資産税の支払いが難しくなることは、珍しいことではありません。とくに収入が減る時期と重なるため、多くの人が負担を感じやすくなります。ここでは、代表的な2つのケースを順に見ていきます。
1:収入が年金だけで額も少ない
老後に収入が年金だけになると、固定資産税は家計を圧迫しやすい支出のひとつです。日本年金機構の公表では、令和7年4月分以降の標準的な年金額は、夫婦2人の厚生年金と老齢基礎年金を合わせて月額23万2,784円とされています。
一方、生命保険文化センターの令和7年度の調査によると、老後の最低日常生活費は月額23.9万円が平均で、標準的な年金額でも毎月およそ7,000円の赤字になります。
個人事業主で国民年金のみの方や、無職期間が長く年金額が少ない方の場合、この赤字はさらに大きくなります。収入が減る一方で固定資産税は毎年必ず発生するため、医療費・介護費などの突発的支出が重なると、固定資産税の支払いが難しくなることも十分にあり得ます。
2:親族から不動産を相続した
両親などの親族から不動産を相続すると、思いがけず固定資産税の負担が発生し、家計に影響が出ることがあります。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、自分が住んでいない空き家であっても所有者として登録されていれば支払いが必要です。
不動産は容易に一部だけを売って納税資金に充てることができないため、準備がないまま相続すると固定資産税が毎年の負担になりやすくなります。さらに、相続税が発生するケースでは家計への影響が一層大きくなります。
相続を意識し始めた段階で、不動産にかかる税金や固定資産税の金額を早めに確認しておくことが大切です。
固定資産税が払えない場合に起こること丨差し押さえまでの流れ
固定資産税を払えないまま放置すると、状況は少しずつ悪化し、最終的には財産の差し押さえに至るおそれがあります。どのような流れで進むのかを知っておくことは、早めの対処につながります。ここでは、延滞から差し押さえまでの具体的なプロセスを順に説明します。
①延滞金が発生する
固定資産税の納期限を過ぎると、翌日から延滞金が発生します。延滞金は、期限どおりに納めた人との公平性を保つために課されるペナルティで、地方税法第369条によって割合が定められています。
納期限の翌日から1か月以内が年7.3%、1か月を超える期間が年14.6%です。滞納が長引くほど金額は増えるため、早めに対応することが大切です。
②自治体から督促状が届く
納期限までに固定資産税を納めない場合、自治体から督促状が送付されます。地方税法第329条では、納期限から20日以内に督促状を発送することが定められています。
督促について、地方税法第331条には以下のように明記されています。
=====================================================================
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
引用元:地方税法 第331条 市町村民税に係る滞納処分
=====================================================================
つまり、督促状が発送されてから10日以内に納付しなければ、自治体には差し押さえの権限が発生します。督促状を放置すると、納税の意思がないと判断されやすくなり、強制的な財産調査や差し押さえに進む可能性が一気に高まります。
③自治体から催告書が届く
督促状を無視して滞納を続けると、自治体から催告書が送られてきます。催告書は、事実上の最終警告であり「このまま滞納が続けば財産を差し押さえる」という内容が明確に記されています。書面に加えて、電話や職員による訪問が行われることもあります。
催告書が届いた段階では、まだ差し押さえは実行されていません。ただし、ここで何の対応もしないままでいると、次の財産調査へと進み、差し押さえが現実的になるため、早めに行動することが大切です。
④財産調査が行われる
催告にも対応しないままでいると、自治体の徴税吏員によって財産調査が行われます。この調査は滞納者の承諾を必要とせず、強制的に実施されます。
対象は官公署、金融機関、勤務先、取引先など幅広く、預貯金の残高や不動産の所有状況、給与の支給状況まで詳しく把握されます。会社勤めの方の場合、勤務先に滞納の事実が知られてしまう可能性があり、社会的信用を損なうリスクも生じます。
⑤財産を差し押さえられる
財産調査で差し押さえ可能な財産が確認されると、自治体は地方税法第373条に基づき差し押さえを実行します。
【差し押さえの対象】
- 不動産(強制退去)
- 預貯金
- 給与
- 動産(現金、貴金属、自動車など)
- 保険の解約返戻金
一方で、国税徴収法により衣服や寝具、3か月分の食料といった生活必需品は差し押さえが禁止されています。
また、国民年金・厚生年金の差し押さえも法律で禁止されているため、差し押さえ時点で受け取り予定の年金は対象外です。ただし、すでに受け取った年金は預貯金として差し押さえの対象になるため注意しましょう。
不動産や動産は公売にかけられ、売却代金が滞納税の支払いにあてられます。自宅が公売にかけられた場合、買い手がつけば強制的に退去しなければなりません。公売は任意売却より売却価格が下がりやすいため、この段階に入る前に対応することがとても重要です。
老後に固定資産税が払えない場合の対処法
固定資産税を払えない状況になっても、適切に対処すれば改善できる可能性があります。重要なのは、放置せずに早めに行動することです。ここでは、自治体への相談から資金調達まで、現実的に取り得る対処法を順に説明します。
まずは自治体の窓口に相談する
固定資産税の支払いが難しくなったときは、まず自治体の窓口に相談することがもっとも重要です。督促状や納付書には担当窓口の連絡先が記載されているため、できるだけ早く連絡しましょう。とくに重要なのは「納税する意思がある」と明確に伝えることです。
督促状や催告書を放置すると、納税の意思がないと判断され、差し押さえに進む可能性が一気に高まります。放置せず早めに相談すれば、分納や減免、徴収猶予などの制度を利用できる可能性があり、担当者から状況に合った対処法を提案してもらえます。
救済措置を利用する
自治体に相談すると、状況に応じて次のような5つの救済措置を利用できる可能性があります。
【分納】
固定資産税を分割して納める方法です。通常は年4回払いですが、自治体によっては毎月払いなど、より細かい分割に変更できる場合があります。分割回数は相談の上で決まります。
ただし、分納が認められた後に滞納し、計画通りに納税できないと差し押さえのリスクが生じます。
【徴収猶予】
病気やケガ、廃業、災害などで納付が難しい場合、原則1年を限度に徴収が猶予されます。猶予期間中は延滞金が全部または一部免除され、新たな督促や差し押さえも行われません。すでに財産が差し押さえられている場合でも、申請すれば解除される可能性があります。
【減免】
支払う税額そのものを軽減または免除する制度です。生活保護受給者、65歳以上で生活に困っている方、障がい者で生活困窮者、災害被害を受けた方などが主な対象です。適用条件は自治体ごとに異なるため、事前の確認が必要です。
【換価の猶予】
すでに差し押さえを受けている財産の売却を一時的に猶予する制度です。納税すると生活の維持が難しくなる場合に認められ、原則1年間の猶予を受けられます。猶予期間中は延滞金が軽減されますが、財産目録や収支明細書の提出、担保の提供が必要になります。
以下は、静岡市の換価の猶予申請可能な対象者についての情報です。
=====================================================================
換価の猶予
市税を一時に納付することによって事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、
かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、猶予を受けようとする市税の
納期限から6か月以内に申請することにより換価の猶予が認められる場合があります。
※申請する市税以外の市税に滞納がある場合は、原則、換価の猶予の申請はできません。
引用元:静岡市|猶予の申請手引き
=====================================================================
【滞納処分の停止】
滞納処分によって生活が著しく困難になる場合に適用される制度です。認められると滞納税の支払い義務はなくなりますが、要件は非常に厳しく、適用例は多くありません。
要件は以下の通りです。
- 滞納処分をすることができる財産がないとき
- 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあること
- その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であること
出典:税務研究会「地方税法 第15条の7 滞納処分の停止の要件等」
不動産を売却する
分納や徴収猶予を利用しても固定資産税の支払いが難しい場合は、不動産を売却する方法もあります。売却して所有権が買主へ移れば、その時点で固定資産税の納税義務はなくなります。
売却によってまとまった資金を得られれば、滞納税の支払いだけでなく、当面の生活費を確保できる点も大きなメリットです。
また、公売と比べて通常の不動産取引の方が高く売れる可能性が高いため、早めに不動産会社へ査定を依頼することが大切です。ただし、1月1日以降に売却した場合は、その年の固定資産税が原則として売主負担になる点には注意しましょう。
リースバックを利用する
住み慣れた自宅を手放したくない場合は、リースバックという方法があります。リースバックとは、自宅を一度売却し、その後は家賃を支払うことで同じ家に住み続けられる仕組みです。
リースバックのメリットは、所有権が買主に移転するため「固定資産税の支払い義務がなくなる点」です。不動産会社が買主となるケースが多く、比較的短期間で売却できるのも特徴です。
一方で、売却価格が市場価格より安くなる傾向があり、賃料が周辺相場より高くなる可能性があるデメリットがあります。賃貸借契約には期間があり、更新できない可能性もあります。買い戻しを希望しても売却時より高い価格が提示される場合があり、確実に買い戻せるわけではない点に注意が必要です。
リバースモーゲージを利用する
リバースモーゲージは自宅を担保にした借り入れであり、リースバックと異なり所有権は移転しません。自宅の所有権を維持したまま資金調達できるのが特徴で、生存中は利息のみを支払えばよいため毎月の負担を抑えられます。
さらに、資金使途は原則自由で、老後の生活費や固定資産税の支払いにも利用可能です。また、一定の条件を満たせば配偶者が契約を引き継げるケースもあります。
不動産担保ローンを利用する
不動産担保ローンは、土地や建物を担保にして資金を借りる方法です。不動産を手放さずにまとまった資金を確保でき、資金使途も原則自由なのが特徴です。
【利用できる主な目的】
- 固定資産税の支払い
- 生活費・医療費
- 事業資金
- 他の税金の納付など
無担保ローンより低金利で、長期返済計画を立てやすい点もメリットです。
固定資産税の支払いをはじめ、生活費、事業資金、ほかの税金の納付など、幅広い目的に利用できます。無担保ローンより低金利で借りられ、長期の返済計画を立てやすいのもメリットです。
とくに注目すべきなのは、固定資産税を滞納している場合でも融資を受けられるケースがあることです。
金融機関によっては、滞納明細や納付書を提出し、融資金を納税に充てることを条件に借り入れが認められる場合があります。審査が順調に進めば最短2日程度で融資を受けられることもあり、督促状が届いて急いで納税したい状況にも対応できます。
ただし、借りたお金は返済が必要で、返済できない状態が続くと担保不動産が処分されるリスクがあります。
【利用時の注意点】
- 借りた資金は当然返済が必要
- 返済不能が続くと担保不動産が処分されるリスクあり
- 収支に無理のない範囲で計画的に利用することが重要
不動産担保ローンは、自宅を手放さずに迅速かつ柔軟に資金調達ができるため、老後の固定資産税問題に悩む方にとって有力な選択肢といえます。
こちらの記事では、納税資金について解説しています。
納税資金の種類や資金不足の際の対処法も取り上げているため、ぜひあわせてご覧ください。
まとめ
老後に固定資産税が払えなくなる状況は、年金生活への移行や不動産の相続など、誰にでも起こり得る問題です。滞納すれば延滞金の発生から督促、財産調査へと進み、最終的に差し押さえに至る可能性がありますが、早めに対処すれば回避できます。
【差し押さえ回避のために】
- 督促を放置しない
- 滞納前に早めに相談する
- 使える制度を把握する
まずは自治体へ相談し、納税の意思を示すことが重要です。分納や徴収猶予、減免などの救済措置が利用できる場合があります。より根本的に資金を確保したい場合は、不動産の売却、リースバック、リバースモーゲージ、不動産担保ローンといった選択肢も検討できます。
とくに不動産担保ローンは、自宅を手放さずに資金調達できる有力な方法です。ワコーファイナンスでは無料のスピード査定審査を実施しており、融資が可能か迅速にご確認いただけます。
老後の生活を守るためにも、固定資産税の問題は放置せず、早めの対応を心がけましょう。固定資産税でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
ワコーファイナンスでは、資金使途自由の不動産担保ローンをご検討中の方に向けてお試し診断を承っております。
本記事は正確な情報を掲載するよう努めておりますが、 情報が古くなったりすることもあり、必ずしもその内容の正確性を保証するものではございません。 当該情報に基づいて被った損害については責任を負いかねます。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆