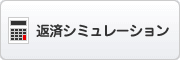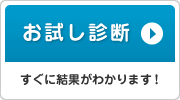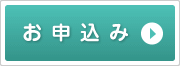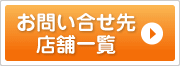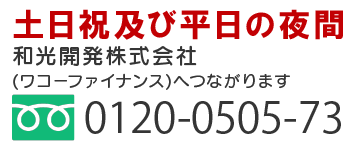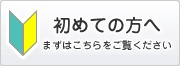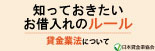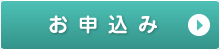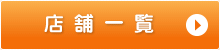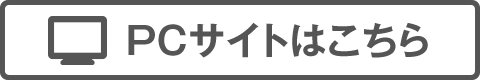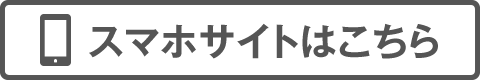名古屋市 堀川祭りのご案内 6月5日
 |
 |
 |
| 2010_堀川まつり 大まきわら船 |
2010_堀川まつり 大山道路引廻し |
2010_「名城・堀川まきわら祭り」 大・中・小まきわら船(2) |
| 1.2012年(平成24年)の予定 |
| 2.堀川まつりの歴史 |
| 3.堀川まつりの記録 |
| 4.あつたっ子/堀川まつりの略歴 |
| 5.名古屋開府400年祭「2010年:名城・堀川まきわら祭り」 |
| 6.まきわら祝い唄 |
| 7.熱田天王祭(南新宮社祭) |
| 8.まきわら船のルーツ:津島天王祭 |
| 9.天王祭りの原点は京都:祇園まつり |
| 10.祭神:牛頭(ごず)天王と素戔嗚尊スサノオノミコト |
| 堀川の天王まつりとまきわら船 |
|---|
| (堀川まつりの歴史) |
| まきわら船の起源は“津島天王祭”。 さらに歴史をたどると“京都祇園祭”がルーツだと言われています。 堀川沿いには洲崎の天王祭、熱田の天王祭が伝わりました。 |
 |
|
|---|---|---|
| <天王祭の流れ> | ||
| まずは上流部、洲崎の天王祭のまきわら船。 尾張徳川家6代藩主宗春のときに最盛期を迎え江戸の2大天王祭りの1つになりましたが、その後、橋の数の増加と明治になり尾張藩千賀水軍の衰退により船が動かなくなり明治21年に中止になりました。 そして下流部の熱田の天王祭は大山。 |
 |
|
| <洲崎天王祭のまきわら船> | ||
| その後熱田の山車は序々に高くなり江戸中期(1754頃にはすでに田中山、大瀬子山などは20m程の高さの日本一の大山になっていました。 祭例日は祇園祭(7月中旬~下旬)と同時期に行なわれており、大山や車楽が町中を引廻しされていました。 熱田 南新宮天王祭は明治になり、市内に電線が架けられるようになり、身動きがとれなくなってきました。 また、南新宮社も明治4年以降に熱田神宮の内にまとめられ、祭例日も尚武祭(6月21日)に統一されました。 明治40年頃天王祭の継続が難しくなったため、熱田浜の人々は大山に替わるものとして、同じ祭神のまきわら船を津島に勉強に行きました。 |
 |
|
| <熱田天王祭の大山> | ||
| そして明治43年(1910) 尚武祭のまきわら船を完成させたのです。 戦争での中断をはさみ、戦後祭例日も熱田まつり(6月5日)に変更になり続けられました。 昭和50年(1975)資金及諸事情のためまきわら船は中止されました。 現在は熱田神宮内で熱田まつりの献灯まきわらとして続けられています。 平成2年(1990)市民グル-プにより、ミニサイズではありますが、堀川まつり(熱田天王祭)のまきわら船として復活され、6月の第1土曜日に堀川流域で行われました。 平成9年からまきわら船は、洲崎神社まで遡るようになり、洲崎と熱田をつなぐ役割を担っています。 |
 |
|
| <熱田まつりのまきわら船> | ||
| 平成17年市民グループはNPO法人化され、念願の大まきわら船が復活。 開催日も津島天王まつりと同時期の7月最終土曜日に変更され、新たに水掛祭りや、大山イメージ櫓も復活の試みが追加され、まきわら船と大山が融合した、若者達の参加しやすい祭りへと変身しようとしている。 |
 |
|
| <大まきわら船と大山イメージ櫓の試し曳き> | ||